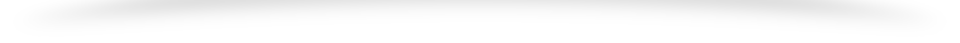高齢者白書(令和元年版)によれば、総人口(2018年10月1日現在)に占める65歳以上の割合(高齢化率)は28.1%と過去最高となりました。統計表示から分かるとおり高齢者とは65歳以上の人(国連の世界保健機関(WHO)の定義)としています。
一方2017年に日本老年学会・日本老年医学会は支えられる側の定義・区分「高齢者」を75歳以上、65~74歳を「准高齢者」とし社会の支え手とする提言をしています。医療の進歩や生活・働く環境等の変化で元気な人も増えている現実から言えば、上記の提言は個人的には納得です。但し、65~74歳の「准高齢者」を支え手と捉えると、雇用や社会保険関係も変わらざるを得ません。単に高齢者の定義・区分の変更だけではないことも理解しておきましょう。今こそ高齢期の働き方・生き方に対する自覚が若い時から求められます。
今後総人口が減る中65歳以上人口増加で高齢化率は上昇することが見込まれています。 しかし、長生きになった人生をどう生きたらいいのか自分のこととして具体的に対策をたてている人は多くはありません。長寿化により最期まで自分らしく生きる知恵も必要になってきました。今回は、長生きリスクが溢れる昨今、逆に元気で長生きなら、就労収入を増やしながら年金受給期間を増やせるメリットもあることを知って年金を積み立てて欲しい願いを込めてお話しします。

2065年に約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上
65歳以上の人口は、団塊世代が65歳以上となった平成27年(2015年)に3,387万人となった後も増加し、令和24年(2042年)に3,935万人と、ピークを迎えると推計されています。総人口が減少する一方で65歳以上が増えていくため、高齢化率は上昇を続け令和47年(2065年)には38.4%となり国民の約2.6人に1人が65歳以上です。また、75歳以上は25.5%であり約3.9人に1人が75歳以上ということになると推計されています。(下図参照)
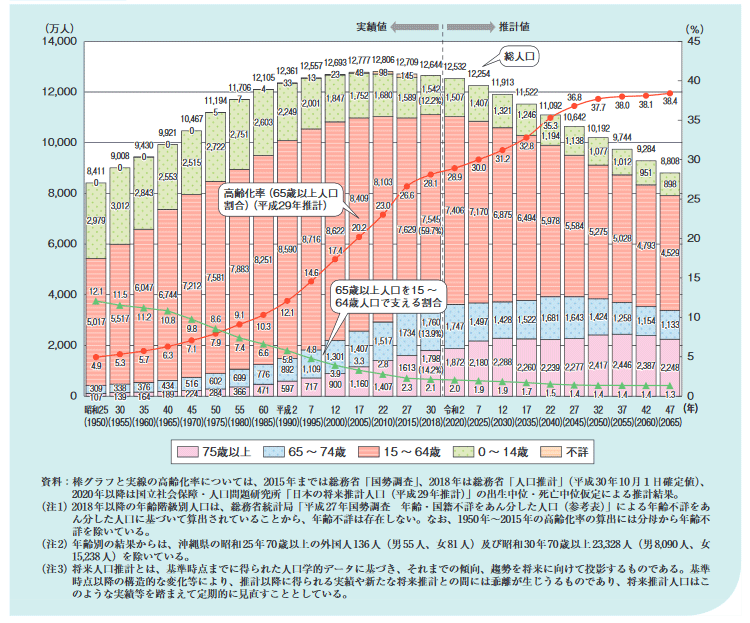
支えられる高齢者とは70歳以上と8割が回答~60歳以上に聞く~
一般の人が捉えている高齢者のイメージは何歳かと言うと、60歳以上や65歳以上と答えた人は少なく約8割の人が70歳以上と答えています(令和元年 高齢者白書)。60~74歳は75歳以上と答えた人が多く、75歳以上は80歳以上と答えた人が多いといったように、自分の年齢より高い年齢を上げています。皆さんお元気でご自身を高齢者と思っていないのですね。支えられる人の意識も年齢だけでは判断できなくなってきつつあります。
| 支えられる高齢者 | |||||||||
| 60歳以上 | 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 | 80歳以上 | 85歳以上 | 年齢では判断できない | 不明 | ||
| 回答者の年齢 | 全体 | 1.3% | 4.5% | 20.1% | 28.1% | 28.4% | 6.5% | 9.7% | 1.4% |
| 60~64歳 | 1.5% | 8.9% | 21.2% | 29.0% | 28.6% | 2.6% | 6.7% | 1.5% | |
| 65~69歳 | 1.1% | 4.2% | 26.3% | 32.8% | 23.2% | 3.8% | 8.0% | 0.6% | |
| 70~74歳 | 1.7% | 3.4% | 16.4% | 33.6% | 28.3% | 4.3% | 11.6% | 0.2% | |
| 75~79歳 | 0.6% | 3.6% | 21.2% | 21.2% | 33.3% | 8.3% | 9.6% | 2.2% | |
| 80歳以上 | 2.0% | 4.0% | 14.0% | 21.5% | 30.4% | 13.2% | 12.0% | 2.9% | |
令和元年版 高齢者白書より抜粋
公的年金の健康診断 ~5年に一度の財政検証(2019年)~
公的年金の定期健康診断に相当する「財政検証」の結果と試算結果が報告されました(令和元年8月27日・社会保障審議会・年金部会)。報告によれば2019年度の所得代替率は61.7%、経済成長と労働参加が進めば所得代替率50%を長期的に維持できるとしています。
経済成長と労働参加が進んだ場合の財政検証 ケース1~3の概略は以下のとおりです。
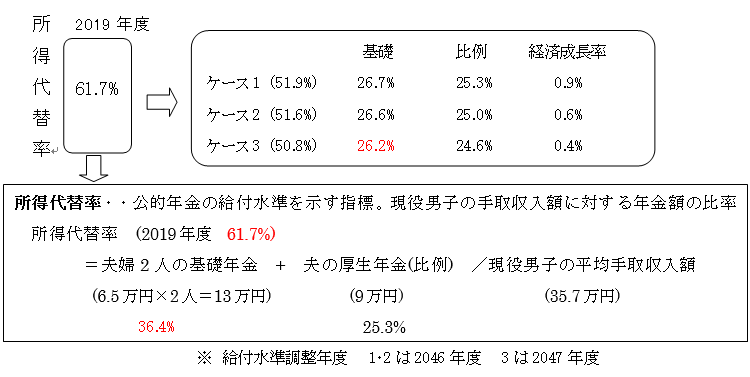
なお試算は、平均寿命、経済成長と労働参加などを仮定して組み立てており確定ではありません。あくまでイメージであり、私たちは今できることを着々と実践していくしかありません。
特に、基礎年金の部分は、36.4%(2019年度)→26.2%(2047年度)と大幅に低下します。
今後の雇用環境の変化を見据えつつ、在職老齢年金や繰下げ、被用者年金(厚生年金)の更なる適用拡大など年金改正を味方にした働き方を検討するのもいいでしょう。
例えば、長生きの女性の場合、厚生年金に加入で厚生年金(報酬比例部分)と国民年金(基礎年金)が両方受給できるため、報酬等が低くても厚生年金加入により加入期間で年金額が決まる基礎年金の効果が発揮でき、高齢期の魅力的収入となるでしょう。
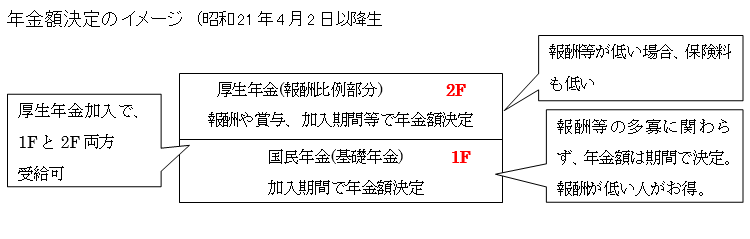
年金額を増やしておけば長生きも怖くない ~長くなる年金受給期間に備える~
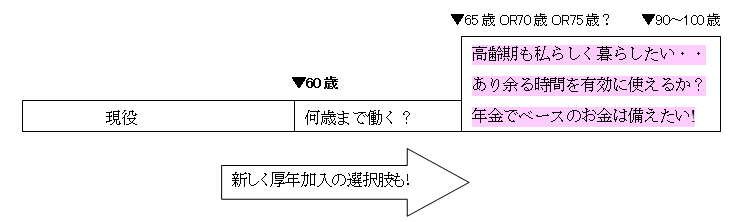
健康で働く目的さえあれば長生きも捨てたものではありません。何しろ人手不足の時代になったのです。趣味だけでは有り余る時間を持てあます人も増えそうです。どんな仕事でも楽しい事ばかりではありません。しかし、苦しみながらもやり遂げたときは充足感があります。
仕事は苦楽しいからやり甲斐があると話してくれた人がいましたが、だからこそ偶の楽しみにワクワクする経験は誰もがお持ちでしょう。人生の主役はあなた。ちょっとした楽しみを企画して遊べるのもベースのお金があってこそ。長生きの時代だからこそ今までよりちょっと長く働いたり、または新しく仕事を始めたりと厚生年金に加入して自分の年金を育て、実りある高齢期を楽しめたら言うことなしですね。
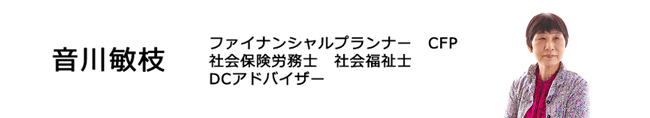
仲間8名と女性の視点からライフプランテキスト作成後、FPとして独立。
金融機関や行政・企業・組合・矯正施設、ハローワーク等で、ライフプランセミナーや年金セミナー等実施。
年金相談や高齢者施設見学を多数実施すると共に、成年後見人等を複数受任し啓蒙セミナーを実施。 専ら、現場主義を貫き人との対話を大切に活動中。
主な執筆歴 読売新聞に「音川敏枝の家計塾」 日経新聞コラム 「社会保障ミステリー」
主な著書に 「年金計算トレーニング BOOK」 ビジネス教育出版
「50歳になったら知っておきたい 年金・介護・高齢期の住まい・成年後見制度・リタイア後のお金入門」
ビジネス教育出版社 他