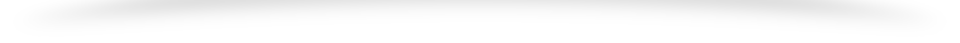今まで年金にあまり興味がなかった人でさえ、「保険料を払った人と払わない人が同じ年金額になるなんて不公平だ!」と声を出し始めた「主婦年金の救済措置(いわゆる運用3号)」。法律を改正しての実施でなく、厚生労働省の課長通達で実施(平成23年1月~)されたことも批判の対象となっています。今回は、そもそもなぜ第3号被保険者が成立したのかを含めてしくみなどについてお話しします。
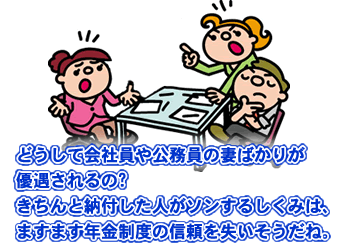
第3号被保険者は昭和61年4月に成立
公的年金は、20歳以上の学生や自営業者、公務員や会社員とその配偶者などが加入し、共通の基礎年金を支給する国民年金と、会社員(公務員など)に基礎年金に上乗せして報酬比例部分(報酬比例部分相当額+職域部分)の年金を支給します。
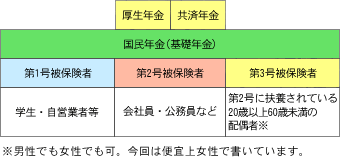
基礎年金が始まったのは昭和61年4月、このとき第1号被保険者と第2号被保険者と今話題の第3号被保険者ができました。第3号被保険者は、会社員などに扶養される配偶者(主に妻)をいいます。それまで妻が会社員などの夫と離婚した場合、妻は無年金または自身の年金が少ないケースが多かったため、妻自身も将来自分の基礎年金を受給できるしくみになったのです。
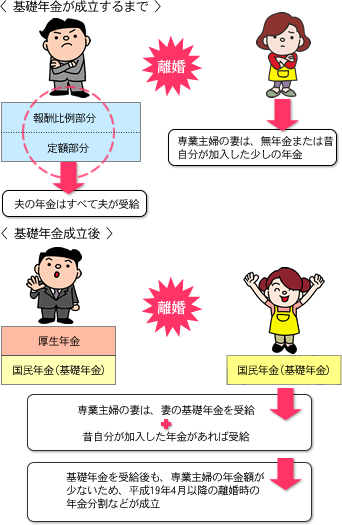
自身で保険料を納付しないが、第3号期間は納付済期間
第3号被保険者の妻は、自身では国民年金の保険料を納付していません。では第3号被保険者分は誰が納付しているのでしょう。夫が加入する厚生年金などの制度で第3号被保険者分を拠出金として国に納付しています。合せて保険料の2分の1を国が負担(税)しています。
夫が退職または自営業者になったとき、専業主婦だった妻が第3号被保険者から第1号被保険者になる手続き忘れが今回の問題点です。自身で納付しないしくみの第3号被保険者が年金に疎くなるのはごく自然かも知れませんね。
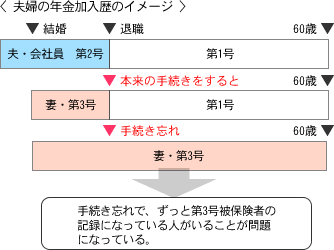
第3号被保険者に対しては、これまでも働く女性などからの疑問もありました。
なぜなら、第3号被保険者の保険料は、厚生年金などに加入した夫だけでなく、働く女性、単身の男性も第3号被保険者の保険料を間接的に負担しているからです。
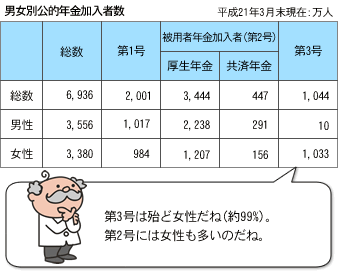
第3号被保険者の存在の検討時期かも
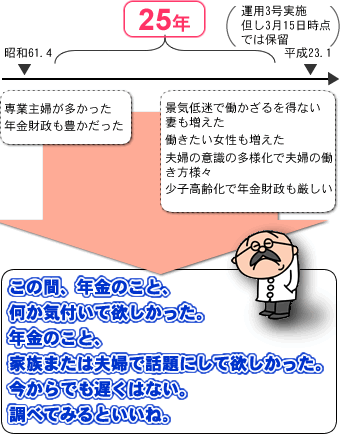
基礎年金制度が成立した昭和61年から運用3号の通達がでるまで約25年経過しています。結婚すれば多くの女性が専業主婦になれた時代は終わり、専業主婦になるのも容易でない時代になりました。国民の誰もが年金のこと、どんな年金に加入し、保険料はいくらか、どんなとき手続きが必要かなど、わが身のこととして意識して学ぶ必要があります。
そろそろ第3号被保険者の存在の可否について国民レベルで真剣に話題とするときが来たかも知れません。
執筆:音川敏枝(ファイナンシャルプランナー)CFP®
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士、DCアドバイザー、社会福祉士。
仲間8名で女性の視点からのライフプランテキスト作成後、FPとして独立。金融機関や行政・企業等で、女性の視点からのライフプランセミナーや年金セミナー、お金に関する個人相談、成年後見制度の相談を実施。日経新聞にコラム「社会保障ミステリー」、読売新聞に「音川敏枝の家計塾」を連載。 主な著書に、『離婚でソンをしないための女のお金BOOK』(主婦と生活社)、『年金計算トレーニングBOOK』(ビジネス教育出版社)、『女性のみなさまお待たせしました できるゾ離婚 やるゾ年金分割』(日本法令)。
HP: http://cyottoiwasete.jp/