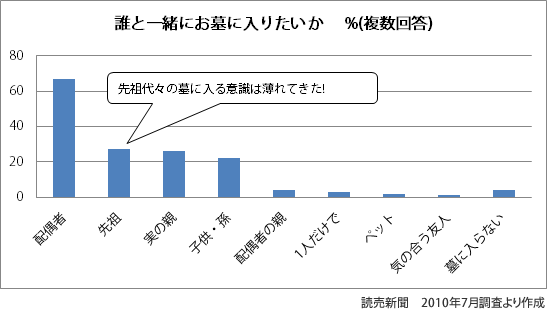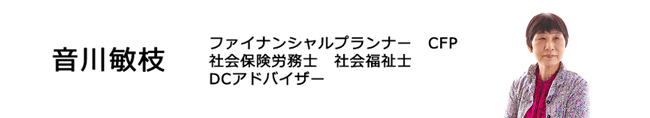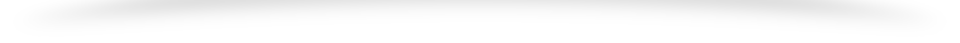お墓参りと親のお見舞い、いつまで続けられるか心配!
先日、ある会が主催する「エンディングノートの書き方」のセミナーを受講しました。数人ずつのグループに分かれ、人生の終末期のことを気軽に討論する有意義なセミナーでした。私のグループは偶然熟年女性ばかりでしたので、逆に本音も聞けた気がします。皆さんのお話しをお聞きして私も思わず頷くことばかり、中高年の悩みは共通しているなーと改めて問題の重さを再認識させられました。数ある悩みの中で、今回は、「お墓」と「高齢者施設に入居する親のお見舞い」などについて我が家の例などもいれながらお話しします。 誰しもが親のことは気になりますが、お墓参りやお見舞いをする側も年齢を重ね体力も少しずつ衰えてきます。自分の代はまだしもこの大変さを子どもの代に強制もできないと感じ初めている人も増えつつあるからです。実際私のお墓に対する考え方も少しずつ変わりつつあります。我が家の場合 ~ お墓が遠い、義母が入居する高齢者施設が遠い!
既に退職している夫と、まだ仕事を続けている私の場合でお話しします。私たち夫婦は、毎年2回1泊2日でホテルに宿泊し両方の家のお墓参りをし、併せて高齢者施設に入居している義母のお見舞いも行っています。それ以外に退職して時間のある夫は、年数回90代の義母が入居している施設を訪問しています。回数が多いか少ないかは人により意見が分かれると思いますが、問題はお墓の場所と施設の場所が遠いということです。 どちらのお墓も交通の便が悪く、夫の田舎の家(今は誰も住んでおらず空家)にあるお墓にはレンタカーを借りて行くことで効率的に動いています。併せて義母が入居する施設の面会時間に合わせて綿密なスケジュールを組んで行動していますが、体力に自信がない私は将来への不安感が募るばかりです。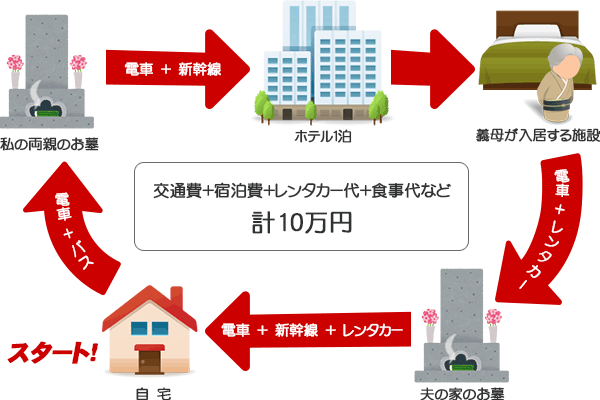
予想される、親世代と次世代の経済的な厳しさ
現在、定年退職後でも働き続けている人も多く、時間的にもお墓と親に対する見守りはこれからもっと厳しくなりそうです。また、公的年金の支給開始年齢が今年60歳の男性から61歳になり、若い世代は将来的には65歳になります。 これからは定年退職後も経済的に働き続けざるを得ない状況です。また、若い世代の雇用が不安定なため、子の扶養を続けざるを得ない人も少なからずいます。セカンドライフも家庭の事情は様々。しかし、確かに言えるのは、今の高齢者を支える世代の現実は年々厳しくなりそうだと言うことです。 遠く離れて暮らしていても、誰しも家や親を思う気持ちは変わりませんが、体力と気力と家計が続く保証はありません。私なども、今は夫婦で協力しあって出かけていますが、私が1人になったとき果たして続けられるか自信がありません。世の人の考えも同じらしく、将来の生活での不安を感じるものの調査でも健康やお金以外にお墓の管理なども上がっています。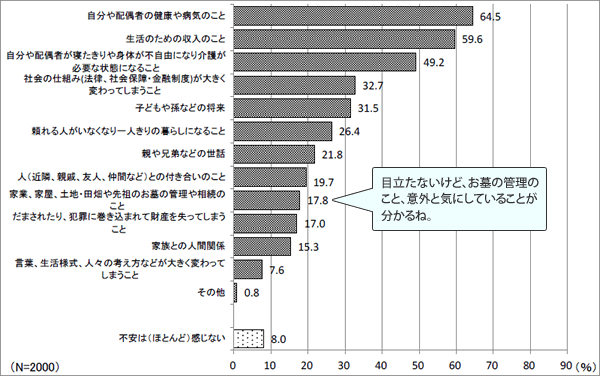
変わりつつあるお墓に対する意識
一族が近くに住み続けられた環境の変化、子どもの減少、単身者の増加、誰と一緒にお墓に入りたいかという意識の変化などもお墓の管理問題を難しくさせているようです。以下の統計でも、先祖代々の墓に入る意識は薄れつつあります。また、田舎のお墓を都会に移すのも、菩提寺の僧との兼ね合いと費用からそう簡単にできない実態もあります。 私もできる限り両方の家のお墓参りは続けるつもりですが、「自分のお墓」に対しては執着がなくなりました。花木が好きなので「樹木葬」、または「散骨」、「納骨堂(ロッカー型)、など今模索中です。お墓に入る私たちとお墓参りする子どもたち両方が、経済的にも精神的にも気楽になれそうな気がするからです。但し、お墓は自分だけの問題ではありません。 特に配偶者の意思の確認も大切です。お墓に関しては一般的に男性の方が保守的という統計もでています。私の場合も、いろいろこれから山坂ありそうです。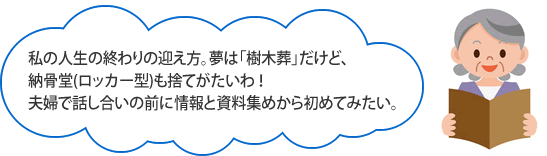
参考までに
「樹木葬」とは、あらかじめ都道府県から「墓地」として認められた里山や民間霊園で遺骨を土に埋め、樹木・花木を「墓碑・墓標」とするものです。半径1㎡ほと゜の区画ごとに専用の木を植える「個別墓」や、1区画1本でなく、1本の木の下で皆が眠る「集合墓」などいろんな形態があります。いずれも自然環境を配慮した点が特徴です。埋葬には通常の墓地と同じように「埋葬許可証」が必要です。 「納骨堂(ロッカー型)とは、お墓の集合住宅です。無縁になっても年に数回合同法要にて永代供養されます。維持管理の手間がかからないのも魅力です。 「散骨」とは、一般には、火葬した後の焼骨を粉末にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送法です。